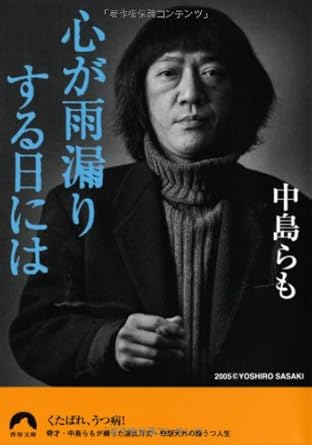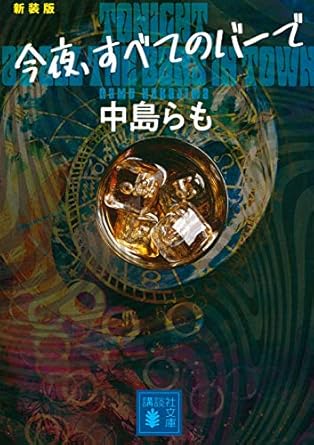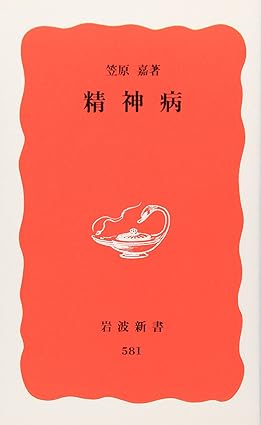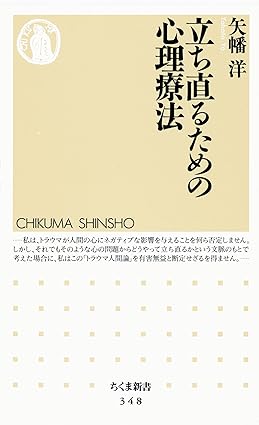2006年7月8日(土)
鑑賞文をお送りいただいた。高専の国語の授業を観て詠めるで、7首をお送りした高専の国語の先生からだ。何しろ、書評のプロ、である。
「水面」の二首に寄せて
水面の小ひさき波紋泡をなし喘ぎたる魚術知らぬ吾
残照がやはらかにさす水面と木々から雲へ乱るる蜻蛉
この二首には、「水面」に投影された「吾」の心象風景が詠み込まれている。これらを連作として読んでみたい。
一首目の「水面」は、小さく揺れている。水中に生きる魚であるはずなのに、今はどうだ、水面から姿を現わして喘いでいるではないか。それを眼前にする「吾」の心はとたんに苦しくなるが、なす術はない。魚に対しても、そして自分自身に対しても。下の句は、「魚」と「吾」の重なりが「波紋」と同調して動的に表現されており、巧みである。
やがて魚は水中へと帰っていき、「水面」の波紋もおさまっていく。「吾」の思索の時間がゆるやかに流れていき、揺れていた「吾」の心もやがて風景の一部となって落ち着いていくのだった。
二首目の「水面」は静かである。残照は、「水面」をなだめるかのように「やはらか」でやさしい。この光によって、疲労を体に残したままではあるが、「吾」の心は癒されていく。時が佇んだかのような静謐な夕暮れの風景だ。だが、ふと仰ぐと蜻蛉が乱れ飛んでいるのが「吾」には見えるのだった。人によっては、ただ美しい風景かもしれないが、ようやく整えることのできた「吾」の心には、小さな波紋が再来するのであった。
魚が「喘ぎたる」のも、蜻蛉が「乱るる」のも、それは「吾」の生物への感情移入によった表現であろう。「吾」の小さき生物へのまなざしはとても優しい。そんな優しく傷つきやすい歌詠みの心の「水面」は、日常の喧噪によって幾度も「波紋」におそわれる。時に自然の風物に癒されつつも、完治することのない深い傷は、その度に疼きだすのである。
人々は程度の差こそあれ、誰しも「波紋」と折り合いをつけながら毎日を過ごしている。けれども繊細な感性を持つ人にとっては、うまく遣り過ごせないことの方が多い。葛藤は言葉に置き換えられ、定型におさめられて、外部へと押し出されていく。そして傷みや感動を共有できる読者を得ることで、それは「歌」として自立するのだ。
コード依存・解読・発信者主体の古典的コミュニケーションモデルでは、説明のつかないコミュニケーションが、あたしの連ねた文字を媒介として行われている。恐らく、コンテキスト依存・解釈・受信者主体のコミュニケーションモデルの典型例かもしれない。
これまで、何度かコンテキスト依存型のコミュニケーションモデルを説明してきたが、うまくできたためしが無い。昨年は、他人の詠んだ短歌を使って、あたしが「解釈しなおして作った歌」を基に説明してみたのだが、これからは、この鑑賞文を教材に使ってみようと思う。
さて、夏のK大学での集中講義が楽しみだ。


![立川談志 古典落語特選 1 [DVD]](https://f.media-amazon.com/images/I/71RqRDmCTlL.__AC_SX300_SY300_QL70_ML2_.jpg)